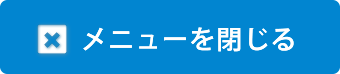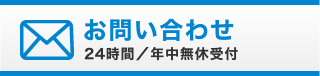ローンを借りる時
印紙税(国税)
内容
金銭消費貸借契約書(ローン契約書)の作成の時に必要
軽減措置
なし
納税の方法
各契約時に契約書の記載金額に応じた印紙を貼付し、消印して納税
| 契約書の記載金額 | ローン契約 |
|---|---|
| 100万円超 500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超 1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円超 5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円超 1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超 10億円以下 | 20万円 |
登録免許税(国税)
抵当権設定登記
税額
債権額×0.4%
軽減措置(建物についてのみ)
債権額×0.1%
適用条件
- 床面積が50m²以上(登記簿面積で)
- 令和4年3月31日までに新築または取得した自分で住むための住宅
- 住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗併用住宅
- 新築または取得してから1年以内に登記すること
- 中古住宅は木造建築後20年以内、鉄骨・鉄筋コンクリート造建築後25年以内であること。
- 築年数にかかわらず新耐震基準に適合する事が証明されたもの又は既存住宅売買瑕疵保険にしている加入しているもの
融資手数料(事務手数料)
融資手数料は金融機関ごとに決められていて、住宅金融支援機構のフラット35の場合
定額タイプで3万円-10万円程度、定率タイプで「融資額×最大2%」(いずれも税抜)
となっており、定率タイプの方が、一般的に金利水準が低くなります。
民間銀行ローンではだいたいローン1件当たり3万円程度が目安になります。
保証保険料(ローン保証料)
保証保険は病気、死亡などではない理由で借りた人が返済不能に陥った時に返済を肩代わりしてもらえる保険です。
現在では連帯保証人を立てる代わりに、銀行の指定した保証会社に保証料を支払い、保証を委託するのが主流です。
ここで注意したいのはローン返済を肩代わりしてもらえるといっても、借り入れている人の債務責任が解消されるわけではない点。債権者が金融機関から保証会社に代わるだけなので購入した住宅を売却するなどして返済しなければなりません。ここが生命保険と違うところです。借入計画はくれぐれも慎重に。
団体信用生命保険料
この保険はローンを借りた人が事故や病気、死亡などの不測の事態が生じて返済不能に陥った時に返済を肩代わりしてもらえるというもの。
下の表は住宅金融支援機構のフラット35を利用し、住宅金融支援機構の団体信用生命保険特約制度(機構団信)に加入した場合の保険料です。
借入期間や金利などによって保険料が決まる仕組みになっています。
銀行などではこの保険料を負担してくれるところもあります。
●機構団信特約料の例(借入金額:1,000万円)
| 返済期間 | 総支払額 | 各年の特約料(目安) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 5年目 | 10年目 | 15年目 | 20年目 | 25年目 | 30年目 | 35年目 | ||
| 15年 | 284,200 | 35,800 | 26,400 | 14,300 | 1,400 | - | - | - | - |
| 20年 | 381,500 | 35,800 | 29,100 | 20,400 | 11,000 | 1,100 | - | - | - |
| 25年 | 485,100 | 35,800 | 30,900 | 24,200 | 17,000 | 9,300 | 900 | - | - |
| 30年 | 588,200 | 35,800 | 32,000 | 26,600 | 20,900 | 14,700 | 8,000 | 800 | - |
| 35年 | 692,900 | 35,800 | 32,700 | 28,300 | 23,600 | 18,500 | 13,000 | 7,100 | - |
火災保険料・地震保険料
2019年10月改定(2020年4月時点)
火災保険は建物が火災によって担保価値を失ったときに下りる保険ですが、融資を受ける場合には原則として火災保険への加入が義務付けられています。 住宅金融支援機構の融資を受ける方の場合、機構融資を利用される方のみが加入できる特約火災保険を利用することができ、一般の火災保険に比べて保険料が安いなどのメリットがあります。 また、任意ではありますが特約火災保険に付保する特約地震保険に加入することもできます。
火災保険は建物が火災によって担保価値を失ったときに下りる保険ですが、融資を受ける場合には原則として火災保険への加入が義務付けられています。 住宅金融支援機構の融資を受ける方の場合、機構融資を利用される方のみが加入できる特約火災保険を利用することができ、一般の火災保険に比べて保険料が安いなどのメリットがあります。 また、任意ではありますが特約火災保険に付保する特約地震保険に加入することもできます。
住宅金融支援機構の特約火災保険料
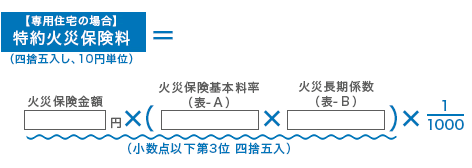
表-A 火災保険料率表 (基本料率)(令和2年4月現在、首都圏のみ抜粋)
|
建物の構造
建物の所在地
|
鉄筋コンクリート 造など |
鉄骨建物など | ツーバイフォー 工法建物など |
木造建物など |
|---|---|---|---|---|
| 東京 神奈川県 |
0.28円 | 0.61円 | 0.61円 | 0.83円 |
| 埼玉県 | 0.27円 | 0.73円 | 0.73円 | 0.92円 |
| 千葉県 | 0.26円 | 0.59円 | 0.59円 | 0.79円 |
表-B 火災保険 長期係数 (保険料一括払いの場合)
| 保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 1.00 | 1.85 | 2.70 | 3.55 | 4.40 | 5.25 | 6.10 | 6.90 | 7.75 | 8.55 |
※平成27年10月から最長保険機関が10年に短縮されました。
住宅金融支援機構の特約地震保険料
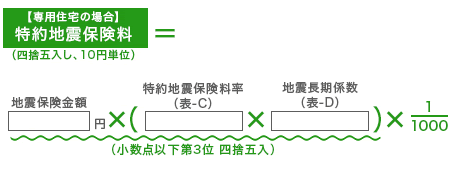
表-C 地震保険料率表
| 鉄筋コンクリート造鉄骨造など | 木造・ツーバイフォー工法建物など | ||
|---|---|---|---|
| 2等地 | 茨城 | 1.37 | 2.86 |
| 3等地 | 埼玉 | 1.60 | 2.86 |
| 4等地 | 東京・神奈川・千葉 | 2.27 | 3.53 |
表-D 地震保険長期係数
| 保険期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 係数 | 1.00 | 1.90 | 2.80 | 3.70 | 4.60 |
※建築年割引や耐震等級割引などの割引制度を活用することによりさらに保険料を下げることもの可能です。