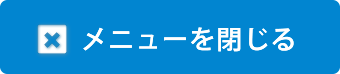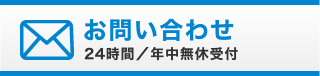買う時に使える特例
特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
住宅ローン控除
自己資金により認定住宅を取得した場合の税額控除
すまい給付金
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70条の2)
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には一定の要件のもと、特例により下記記載の金額まで贈与税が非課税となります。
<非課税限度額>
| 住宅用家屋の取得等に 係る契約の締結期間 |
住宅用家屋に係る消費税10% | 左記以外(注) | ||
|---|---|---|---|---|
| 良質な建物 | 一般の建物 | 良質な建物 | 一般の建物 | |
| 平成28年1月~令和2年3月 | - | - | 1,200万円 | 700万円 |
| 平成31年4月~令和2年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 | ||
| 令和2年4月~令和3年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
| 令和3年4月~令和3年12月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
(注)「左記以外」には消費税8%の適用を受けて住宅用家屋を取得した場合、及び個人間売買により中古住宅を取得した場合が該当します。
東日本大震災の被災者に対しての非課税限度額は下記のとおりです。
| 住宅用家屋の取得等に 係る契約の締結期間 |
住宅用家屋に係る消費税10% | 住宅用家屋に係る消費税8% | ||
|---|---|---|---|---|
| 良質な建物 | 一般の建物 | 良質な建物 | 一般の建物 | |
| 平成28年1月~令和3年3月 | - | - | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 平成31年4月~令和2年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 | - | - |
| 令和2年4月~令和3年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 | ||
適用可否チェックリスト
特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(措法70条の3)
(1)平成15年1月1日から令和3年12月31日までの住宅取得資金贈与においては、贈与者の年齢が60歳未満(平成26年12月31日までは65歳未満)であっても、一定の要件を満たせば相続時精算課税制度の適用が受けられます。
(2)この規定の適用要件を満たし、所定の手続きを経て、この規定の適用を受けることとなった者が、住宅取得資金の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度の適用を受けることができます。
(3)一度この規定を選択した者は、この規定に係る贈与者からの選択後の贈与について、全て相続時精算課税制度を適用し、「暦年課税制度」を適用することはできません。
(4)贈与を受けた住宅取得資金について、この規定の適用を受けることを選択した者の受贈年の合計所得金額が2,000万円以下である場合には、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法70条の2)」の規定の適用も受けることができます。この場合、住宅取得資金から先に控除する金額は、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例(措法70条の2)」の規定に係る非課税限度額です。
(5)住宅の新築に先行して、その敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金は、この規定の住宅取得資金の範囲に含まれます。
適用可否チェックリスト
住宅ローン控除(措法41条)
(1)新築住宅又は既存住宅の取得等(建築を含む)又は既存住宅に対する一定の増改築等をし、平成11年1月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、10年間所得税が軽減されます。
(2)居住用住宅の取得等(その対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限る。)をして、令和元年10月1日から2年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、この規定が適用される期間が10年から13年に延長され最大累積控除額も増加しました。
(3)居住用家屋が一般住宅に該当するか、又は認定住宅に該当するかにより控除額が異なります。尚、認定住宅ついてには、「自己資金もより認定住宅を取得した場合の税額控除との重複適用はできません。
(※)適用要件等について改正があった場合、適用開始年月日が変更される場合がありますので、適用開始年月日は注意して下さい。
控除税額等は下記のようになります。
一般住宅
(1)住宅に係る消費税の税率が8%である場合
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額※ |
控除率 | 年間最大 控 除 額 |
最大累積 控 除 額 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年4月~ 令和3年12月 |
10年間 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |
(2)住宅に係る消費税の税率が10%である場合
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額※ |
控除率 | 年間最大 控 除 額 |
最大累積 控 除 額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年4月~ 令和3年12月 |
13年間 | 1年目~10年目 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 520万円 |
| 2 | 11年目~13年目 | 4,000万円 | 1%の場合 | 40万円 | |||
| 3 | 2.0%÷3 | 26.66万円 | |||||
注1 1年目から10年目までは上記(1)と同じ
注2 11年目から13年目までは次のイ又はロに掲げる金額のいずれか少ない金額
イ. 住宅借入金等の年末残高(1年目から10年目までと同じ、4,000万円を限度)×1%
ロ. 〔取得等した住宅の税抜対価の額(土地の取得に要した金額を含みません。4,000万円を限度)〕×2%÷3
※上記の取得等した住宅の金額とは、次のとおりです。
(イ) 取得等をした住宅のうちにその者の居住用以外の部分がある場合には、その住宅の床面積のうちに居住用部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額です。
(ロ) 取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける場合であっても、その補助金等の額又はその適用を受けた住宅取得等資金の額を控除しないこと。
認定住宅
(1)住宅に係る消費税の税率が8%である場合
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額※ |
控除率 | 年間最大 控 除 額 |
最大累積 控 除 額 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年4月~ 令和3年12月 |
10年間 | 5,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |
(2)住宅に係る消費税の税率が10%である場合
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額※ |
控除率 | 年間最大 控 除 額 |
最大累積 控 除 額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年4月~ 令和3年12月 |
13年間 | 1年目~10年目 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 650万円 |
| 2 | 11年目~13年目 | 5,000万円 | 1%の場合 | 50万円 | |||
| 3 | 2.0%÷3 | 26.66万円 | |||||
注1 1年目から10年目までは上記(1)と同じ
注2 11年目から13年目までは次のイ又はロに掲げる金額のいずれか少ない金額
イ. 住宅借入金等の年末残高(1年目から10年目までと同じ、5,000万円を限度)×1%
ロ. 〔取得等した住宅の税抜対価の額(土地の取得に要した金額を含みません。5,000万円を限度)〕×2%÷3
※上記の取得等した住宅の金額とは、次のとおりです。
(イ) 取得等をした住宅のうちにその者の居住用以外の部分がある場合には、その住宅の床面積のうちに居住用部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額です。
(ロ) 取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受ける場合であっても、その補助金等の額又はその適用を受けた住宅取得等資金の額を控除しないこと。
居住用家屋・土地等を取得した場合の適用可否チェックリスト
既存住宅に対する一定の増改築等をした場合の適用可否チェックリスト
住宅ローン控除額の計算表
自己資金により認定住宅を取得した場合の税額控除(措法41条の19の4)
認定住宅とは
認定住宅とは次に掲げる住宅で、認定住宅に該当することにつき一定の証明がされたもの。
1.認定長期優良住宅とは、「住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅をいいます。
2.認定低炭素住宅とは、「住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する低炭素建築物及び同法の規定により低炭素建築物とみなされる同法に規定する特定建築物(認定集約都市開発事業により整備されるものに限る)をいいます。
自己資金で認定住宅を取得した場合
その年分の合計所得金額が3,000万円以下の居住者が、国内において認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の新築又は取得(建築後使用されたことのないものに限る)をし、下記の期間内に居住の用に供した場合、下記の控除が受けられます。
1.認定長期優良住宅については、平成21年6月4日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供すること。
2.認定低炭素住宅については、平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供すること。
| 住宅の種類 | 居住年 | 控除 期間 |
控除額 | 控除限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 認定長期 優良住宅 |
平成26年6月4日 ~ 令和3年12月31日 |
初年度 (注1) |
【認定住宅に関わる標準的な性能強化費用の額(注2)-補助金等(最高650万円)】×10% | 65万円 |
| 認定低炭素 住宅 |
平成26年4月1日 ~ 令和3年12月31日 |
(注1)この控除は居住年のみ適用がありますが、居住年で控除不足が生じた場合には、その翌年で控除が可能です。
(注2)国土交通省告示で定められている「標準的な性能強化費用の額」が見直されることになりました。新しい「標準的な費用の額」は、新築等した認定住宅を同日以後に居住の用に供した場合に適用されます。
適用可否チェックリスト
すまい給付金
消費税の税率引上げの措置として、平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に、居住用住宅及び土地を取得し居住した一定のものについて、すまい給付金が支払われます。
給付金の額の算式
給付金の額は下記の算式により計算されます。
給付額=給付基礎額×持分割合
給付基礎額
イ.消費税率が8%の場合
| 収入要件の目安 | 道府県民税の所得割 | 給付基礎額 |
|---|---|---|
| 425万円以下 | 68,900円以下 | 30万円 |
| 425万円超~475万円以下 | 68,900円超~83,900円以下 | 20万円 |
| 475万円超~510万円以下 | 83,900円超~93,800円以下 | 10万円 |
ロ.消費税率が10%の場合
| 収入要件の目安 | 道府県民税の所得割 | 給付基礎額 |
|---|---|---|
| 450万円以下 | 76,000円以下 | 50万円 |
| 450万円超~525万円以下 | 76,000円超~97,900円以下 | 40万円 |
| 525万円超~600万円以下 | 97,900円超~119,000円以下 | 30万円 |
| 600万円超~675万円以下 | 119,000円超~140,600円以下 | 20万円 |
| 675万円超~775万円以下 | 140,600円超~172,600円以下 | 10万円 |
※1 神奈川県は、他の都道府県と住民税の税率が異なるため、都道府県民税所得割額が少し違ってきますので注意してください。
※2 住宅ローンの利用がない場合は、目安として収入額が650万円(所得割額は目安として133,000円)を超える者は、この規定の適用を受けることができないので、10万円の欄は使用できなくなることがあります。