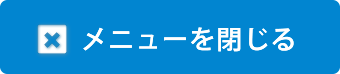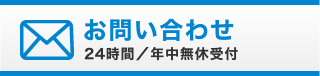不動産取得税の計算方法とは?軽減措置でどこまで安くなる?
不動産を購入する際にかかるお金に目が向きがちですが、不動産購入後には不動産取得税の納付書が送られてきます。認識していなかった出費に驚くことがないように、今回は不動産取得税の基本知識と計算方法、居住用の不動産に適用される軽減措置についてご紹介します。
不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や家屋を取得した際にかかる税金です。土地は、住宅用地はもちろん、田畑、山林、牧場、原野、温泉などあらゆる土地が対象となります。家屋も住宅だけでなく、店舗、工場、倉庫などの建築物が該当します。
有償での購入だけでなく、無償での贈与を受けた際にも不動産取得税はかかります。ただし、相続により不動産を取得した場合は不動産取得税ではなく、相続税の対象となるので不動産取得税はかかりません。
有償での購入だけでなく、無償での贈与を受けた際にも不動産取得税はかかります。ただし、相続により不動産を取得した場合は不動産取得税ではなく、相続税の対象となるので不動産取得税はかかりません。
不動産取得税はいつどこで払う

不動産を取得したら、各自治体の税事務所に不動産を取得した旨を申告しなければなりません。自治体によって申告期限が異なり、東京都の場合は取得から30日以内の申告が義務付けられています。
申告が完了すると毎月7日前後に納税通知書が送られてきます。送られてくるタイミングは直近の7日にすぐ送られてくることもあれば、翌月の7日のこともあり、届くまでわかりません。支払い期日は納税通知書発送月の月末になっています。スマホ決済、クレジットカード、ペイジー、コンビニ払い、税事務所や金融機関の窓口などで支払いが可能です。
ちなみに、不動産登記を先に行った場合は、原則としてあらためての税事務所への申告は不要です。3年以内の不動産登記も義務化されたので、不動産を取得してすぐに不動産登記を行うことで、忘れることを防ぐと同時に、税事務所への申告の二度手間もなくなります。
申告が完了すると毎月7日前後に納税通知書が送られてきます。送られてくるタイミングは直近の7日にすぐ送られてくることもあれば、翌月の7日のこともあり、届くまでわかりません。支払い期日は納税通知書発送月の月末になっています。スマホ決済、クレジットカード、ペイジー、コンビニ払い、税事務所や金融機関の窓口などで支払いが可能です。
ちなみに、不動産登記を先に行った場合は、原則としてあらためての税事務所への申告は不要です。3年以内の不動産登記も義務化されたので、不動産を取得してすぐに不動産登記を行うことで、忘れることを防ぐと同時に、税事務所への申告の二度手間もなくなります。
不動産取得税の計算方法

不動産取得税の基本的な計算方法は
不動産の評価額×税率(4%)=税額
です。
ただし、住宅用土地と家屋に関しては軽減税率の3%が適用されます。
不動産の評価額とは国が定める固定資産税評価額のことです。実際の不動産売買価格ではないので注意しましょう。
家屋の固定資産税評価額に関しては一般的に建築費の7割程度が不動産評価額とされることが多いです。土地の固定資産税評価額に関しては、一般財団法人資産評価システム研究センターの提供する全国地価マップで調べることができます。
全国地価マップ
物件購入前に正確な不動産評価額を知りたい場合は、所有者に教えてもらうか仲介不動産会社に調査を依頼する必要があります。
計算の例ですが例えば下記の場合、
<土地5000万円と家屋1500万円>
(5000万円+1500万円)×0.03=195万円
195万円が不動産取得税となります。
一方、<土地5000万円と店舗用建物1500万円>は、店舗用建物に軽減税率が適用されないので
5000万円×0.03+1500万円×0.04=210万円
210万円が不動産取得税となります。
ちなみに、不動産取得税は、土地と家屋の購入だけでなく、増改築を行った場合も発生します。増改築の場合、土地を買い足ししなければ土地の不動産取得税は当然発生しません。ただし、家屋部分に関しては増改築後に増床等により床面積が増える等で評価額が上がると、上がった分に対して不動産取得税が課せられます。
不動産の評価額×税率(4%)=税額
です。
ただし、住宅用土地と家屋に関しては軽減税率の3%が適用されます。
不動産の評価額とは国が定める固定資産税評価額のことです。実際の不動産売買価格ではないので注意しましょう。
家屋の固定資産税評価額に関しては一般的に建築費の7割程度が不動産評価額とされることが多いです。土地の固定資産税評価額に関しては、一般財団法人資産評価システム研究センターの提供する全国地価マップで調べることができます。
全国地価マップ
物件購入前に正確な不動産評価額を知りたい場合は、所有者に教えてもらうか仲介不動産会社に調査を依頼する必要があります。
計算の例ですが例えば下記の場合、
<土地5000万円と家屋1500万円>
(5000万円+1500万円)×0.03=195万円
195万円が不動産取得税となります。
一方、<土地5000万円と店舗用建物1500万円>は、店舗用建物に軽減税率が適用されないので
5000万円×0.03+1500万円×0.04=210万円
210万円が不動産取得税となります。
ちなみに、不動産取得税は、土地と家屋の購入だけでなく、増改築を行った場合も発生します。増改築の場合、土地を買い足ししなければ土地の不動産取得税は当然発生しません。ただし、家屋部分に関しては増改築後に増床等により床面積が増える等で評価額が上がると、上がった分に対して不動産取得税が課せられます。
不動産取得税を軽減する特例措置とは

さて、実は上記で説明した計算で算出した不動産取得税額をそのまま納税するというケースは、居住用に土地と家屋を取得したケースではむしろ少ないです。理由としては、不動産取得税を軽減する特例措置があるからです。
新築住宅と土地を購入した場合
まず、新築住宅を購入した場合、1戸あたりの床面積が50㎡~240㎡の範囲であれば、1200万円の控除があります。
家屋の評価額から1200万円を差し引いての計算になるという意味です。
つまり、
(不動産の評価額-1200万円)×税率(3%)=税額
これが軽減措置を適用した不動産取得税額の計算式となります。
先ほどの例で<土地5000万円と家屋1500万円>の場合、
(1500万円-1200万円)×0.03=9万円
家屋部分の不動産取得税は9万円となりました。
次に土地ですが、ややこしいです。
(土地の固定資産税評価額×1/2×3%)−(土地1m2あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×取得した住宅の持分×3%)
という計算方法で軽減措置を適用します。後ろの括弧内が控除額にあたります。
80m2の5000万円の土地に床面積100m2の家屋が建っている場合
<先の括弧内の計算>(土地の固定資産税評価額×1/2×3%)
5000万円×1/2×0.03=75万円
<後の括弧内の計算>(土地1m2あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×取得した住宅の持分×3%)
土地1m2あたりの価格:5000万円÷80m2=62.5万円
62.5万円×1/2×100m×2×1×0.03=150万円
そして、この後ろの括弧内で算出された金額を45000円と比較して、高い額が控除額となります。そのため今回は187.5万円が控除額です。
<先の括弧-後の括弧>
75万円-187.5万円=−112.5万円
このようにマイナスになりました。そのため土地の不動産所得税は0円です。
最初に戻り、<土地5000万円と家屋1500万円>を購入した場合の合計の不動産所得税は
9万円(家屋部分)+0円(土地部分)=9万円
9万円が不動産取得税となります。
家屋の評価額から1200万円を差し引いての計算になるという意味です。
つまり、
(不動産の評価額-1200万円)×税率(3%)=税額
これが軽減措置を適用した不動産取得税額の計算式となります。
先ほどの例で<土地5000万円と家屋1500万円>の場合、
(1500万円-1200万円)×0.03=9万円
家屋部分の不動産取得税は9万円となりました。
次に土地ですが、ややこしいです。
(土地の固定資産税評価額×1/2×3%)−(土地1m2あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×取得した住宅の持分×3%)
という計算方法で軽減措置を適用します。後ろの括弧内が控除額にあたります。
80m2の5000万円の土地に床面積100m2の家屋が建っている場合
<先の括弧内の計算>(土地の固定資産税評価額×1/2×3%)
5000万円×1/2×0.03=75万円
<後の括弧内の計算>(土地1m2あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×取得した住宅の持分×3%)
土地1m2あたりの価格:5000万円÷80m2=62.5万円
62.5万円×1/2×100m×2×1×0.03=150万円
そして、この後ろの括弧内で算出された金額を45000円と比較して、高い額が控除額となります。そのため今回は187.5万円が控除額です。
<先の括弧-後の括弧>
75万円-187.5万円=−112.5万円
このようにマイナスになりました。そのため土地の不動産所得税は0円です。
最初に戻り、<土地5000万円と家屋1500万円>を購入した場合の合計の不動産所得税は
9万円(家屋部分)+0円(土地部分)=9万円
9万円が不動産取得税となります。
中古住宅と土地を購入した場合
中古住宅の場合も軽減措置の計算方法は基本的には新築住宅と同じですが、新築された時期により控除額が異なります。
平成9(1997)年4月1日以降の場合 1,200万円
平成元(1989)年4月1日~平成9(1997)年3月31日の場合 1000万円
昭和60(1985)年7月1日~平成元(1989)年3月31日の場合 450万円
昭和56(1981)年7月1日~昭和60(1985)年6月30日の場合 420万円
昭和51(1976)年1月1日~昭和56(1981)年6月30日の場合 350万円
このように新築時期が古くなればなるほど控除額が減る仕組みになっています。そして、この控除を受けるためには現在の耐震基準に適合している必要があります。計算式は
(不動産の評価額-控除額)×税率(3%)=税額
となります。
例えば1988年に新築された、<土地5000万円と家屋600万円>の中古住宅の場合
<家屋部分>
(600万円-450万円)×0.03=4万5000円
<土地部分>
先ほどと同じ計算方法のため省略。0円。
4万5000円(家屋部分)+0円(土地部分)=4万5000円
4万5000円が不動産取得税となります。
平成元(1989)年4月1日~平成9(1997)年3月31日の場合 1000万円
昭和60(1985)年7月1日~平成元(1989)年3月31日の場合 450万円
昭和56(1981)年7月1日~昭和60(1985)年6月30日の場合 420万円
昭和51(1976)年1月1日~昭和56(1981)年6月30日の場合 350万円
このように新築時期が古くなればなるほど控除額が減る仕組みになっています。そして、この控除を受けるためには現在の耐震基準に適合している必要があります。計算式は
(不動産の評価額-控除額)×税率(3%)=税額
となります。
例えば1988年に新築された、<土地5000万円と家屋600万円>の中古住宅の場合
<家屋部分>
(600万円-450万円)×0.03=4万5000円
<土地部分>
先ほどと同じ計算方法のため省略。0円。
4万5000円(家屋部分)+0円(土地部分)=4万5000円
4万5000円が不動産取得税となります。
不動産取得税を頭に入れて物件購入を検討しよう

不動産取得税の軽減措置が適用されるのは、耐震基準に適合していることが条件です。現在新たに建てられる新築住宅であれば100%適合しているはずですが、中古住宅をリフォーム等せずに購入する場合、軽減措置の適用外になる可能性があります。軽減措置を適用するために購入後に改めてリフォームの計画を立てるのは大変です。他にも、200m2以上の床面積の部分は軽減措置が適用されないと言った細かいルールがたくさんあるので、物件購入の際には必ず不動産取得税の軽減措置が適用されるか、検討している物件はいくらの不動産取得税を支払う計算になるのか、不動産会社に確認しましょう。購入後に税務署から高額の納付書が送られてきて驚くということも起こり得ます。
https://www.8111.com/info/qanda/
https://www.8111.com/info/qanda/